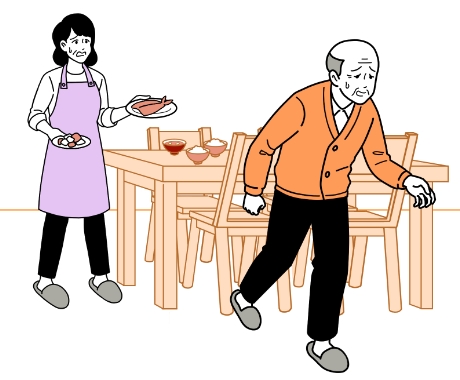01
否定せず、共感を示しましょう

広い視野で捉え、なぜそのような言動をとっているのか
ご本人の気持ちを理解することから始めましょう
認知症の方は、記憶障害の影響により、自分が何をどこに置いたかを忘れて「物を盗られた」と思い込んでしまうことがあります。こうした症状は「物盗られ妄想」と呼ばれます。
このとき、認知症の方は大切な物がなくなったと思い、不安や恐怖、混乱を抱えていることも少なくありません。そのため、単に「盗っていない」と否定することは、不安や不信感を強めることにつながりかねません。まずは「どこにあるか心配だよね」といった言葉で共感を示す姿勢が大切です。
また、このような妄想の背景には、認知機能障害によるご自身の能力や役割、生活などにおける喪失感があります。家事の手伝いやデイサービスでの活動など、無理のない範囲でご自身の役割が感じられる機会を提供するとよいでしょう。日々の達成感の積み重ねによって自己肯定感は高まり、喪失感を和らげることが期待できます。
ただし、ここに挙げた出来事は一例に過ぎず、ご本人が抱える苦悩はさまざまです。理由や対処法は一様ではありませんので、ご本人の状況や気持ちを確認しながら、それに応じた個別の対応をとることが大切です。
02
安心できる形で事実を伝えましょう


「通帳は私がちゃんと保管しているし、いつでも確認できるからね」など、事実を「安心できる」形で伝えましょう
こちらに示した例のように、家族が預かって管理している場合は、「通帳は私がちゃんと保管していますよ。いつでも確認できるからね」などと、その事実を「安心できる」形で伝えることが大切です。
また、大切な物は置く場所を決め、部屋を整理整頓された状態にしておくことおすすめします。ただし、常に見える所に置いておくと別の場所にしまいこんでしまう可能性がありますので注意が必要です。認知症の方は「盗られた」と思うと、より見つけにくいところにしまいこむ傾向があり、その後、しまった場所がわからなくなるという悪循環を引き起こします。整理された環境は、物を探す際の混乱を軽くするのに役立つとともに、認知症の方にとっても安心できる場所として認識されますので、日頃から生活環境を整えておくとよいでしょう。
03
周りのサポートを利用し、
介護する方もリフレッシュしましょう
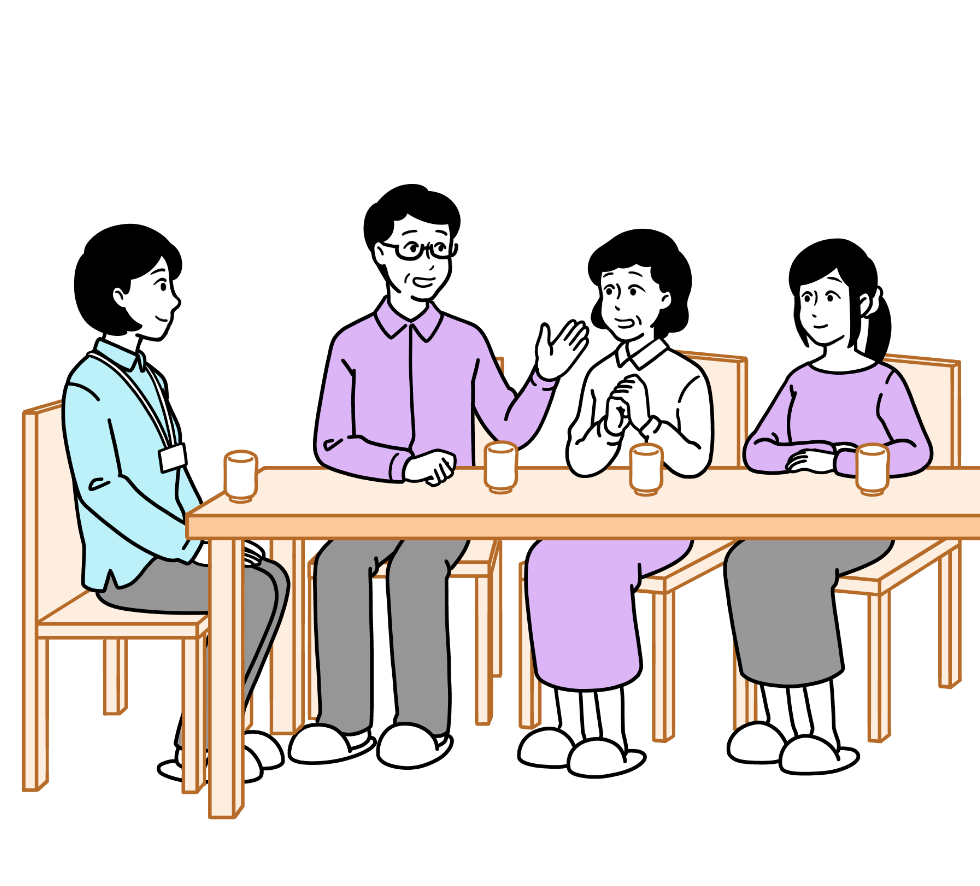
家族会などで悩みを共感してもらうことは気持ちの助けになります
物盗られ妄想は、家族などの身近な人へ疑いの目が向けられる傾向にあります。大切に思っている人から「物を盗られた」と疑われることは、介護する家族にとってつらい経験です。疑われたときに湧き上がる驚きや悲しみ、怒りなどのさまざまな感情は無理に抑え込もうとせず、自分の気持ちをしっかり受け止める時間を持つことが大切です。家族会や認知症カフェを通じて、共感し合える介護経験者に話を聞いてもらったり、ケアマネージャーなどの専門スタッフに相談することで感情の整理がしやすくなります。
また、疑いの目が特定の人にばかり向けられる場合は、他の家族からも誤解される可能性があり、大きな孤立感を抱くことになりかねません。そのようなときは少し距離をおいてみることも検討してみてください。他の家族やデイサービス、訪問介護サービスなど周りのサポートを受けながら、介護する方がリフレッシュする時間を確保することも重要です。
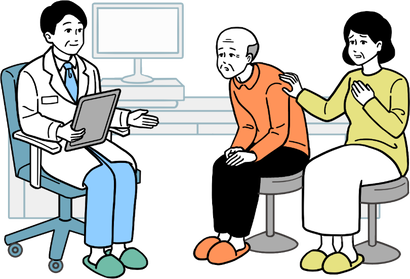
こちらにご紹介した症状および対処法は一例であり、すべての認知症の方に当てはまるわけではありません。個別の状況に応じた対処法は異なりますので、このような症状でお困りの方は、ぜひ主治医に相談してください。
主治医に相談する際のポイントをまとめた、こちらの「相談シート」をぜひ活用してください。