脳科学から見た統合失調症
統合失調症を科学的な視点から解説しています。
監修:仙波純一先生
さいたま市立病院
3.統合失調症の治療薬
3-1抗精神病薬はどのように作用するか
統合失調症の治療の中心になる薬物を抗精神病薬といいます。この抗精神病薬の発見は約50年前にさかのぼることができます。
当時特殊な麻酔のために使う薬として開発していたクロルプロマジンという薬物に、統合失調症の症状を改善する効果のあることが発見されたのです。
それ以前に使われていた薬物は、たんに興奮を抑えるような鎮静薬にすぎなかったのです。
抗精神病薬の発見によって、統合失調症の治療法が大きく変化しました。
抗精神病薬は精神症状の改善だけでなく、再発予防効果もありますから、入院中心の治療から外来での治療へという、現在の統合失調症の治療方針が確立したのもこの薬によるといってもいい過ぎではありません。
さて、このようないきさつで見つかった抗精神病薬ですが、その作用の仕組みはしばらくわかりませんでした。
1960年ごろから脳内での神経伝達の仕組みが生化学的に調べられ始めると、抗精神病薬は脳内にある神経伝達物質であるドーパミンの情報伝達を抑制するということがわかりました。
図1にドーパミンの神経伝達が行われるドーパミンのシナプスをやや詳しく示しました。
第2章で述べたように、抗精神病薬はドーパミンの受容体(中でもD2とよばれる受容体)を占拠してしまい、ドーパミンが受容体に結合するのを阻止するのです(図2)。
実際、カナダのシーマンという研究者は多くの有効とされている抗精神病薬の投与量とドーパミンD2受容体の占拠率とのあいだに、強い関係のあることを示しました(図3)。
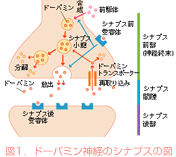
【図1】ドーパミンは前駆体からシナプスの前部(情報を伝える側の神経細胞の末端)で合成され、シナプス小胞という小さな袋に蓄えられます。
神経のインパルスが伝わってくると、このシナプス小胞はシナプス間隙側に移動して、中にあるドーパミンを細胞外に放出します。
放出されたドーパミンはシナプス後部(情報の受け側の神経細胞)にあるドーパミン受容体に結合して、シナプス前部からの情報を後部に伝えます。
また、一部のドーパミンは分解されたり、再びシナプス前部にトランスポーターを使って取り込まれたりして、不活化されます。
ドーパミン受容体はシナプスの前部にもあり、シナプス前受容体とか自己受容体などとよばれています。
この受容体はドーパミンの合成や遊離などに対して抑制的に働くために、自己調節機能を持っていることになります。
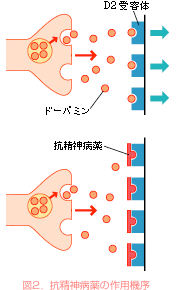
【図2】抗精神病薬はドーパミン2型受容体(ドーパミンD2受容体といいます)を占拠して、ドーパミンの結合を阻害します。その結果、ドーパミンの神経伝達が抑制されます。
この抗精神病薬の働きから考えると、統合失調症ではドーパミンの機能が過剰なのではないかと考えられます。これを統合失調症のドーパミン仮説といいます。
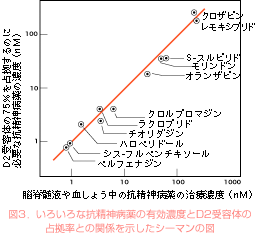
【図3】抗精神病薬の投与量は必ずしも脳内の濃度と比例しないため、ここでは脳脊髄液か血しょう内の濃度で代表しています。
いろいろな抗精神病薬があっても、その抗精神病効果に関連しているのはドーパミンD2受容体への遮断作用であることを示す強い証拠の一つです。
これは、抗精神病薬にはいろいろな種類があるにしても、すべて共通してドーパミンD2受容体の遮断という薬理作用を持っていることを示しています。 このような抗精神病薬の作用機序から統合失調症のドーパミン仮説が生まれてきたことについてはすでにお話ししました。 現在多くの抗精神病薬が使われていますが、どれもD2受容体の阻害作用を持つ薬物の中から見いだされたものです。
3-2-1抗精神病薬はどのように作用するか
現在発売されている抗精神病薬は、みな同じように統合失調症に対する効果を持っています。しかし、副作用は薬によって少しずつ違っています。口渇・便秘・かすみ目などは抗コリン作用といって、抗精神病薬が神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を阻害するためです。
また、立ちくらみや眠気は、神経伝達物質であるアドレナリンやヒスタミンの作用の阻害だろうと考えられています。
このような副作用は、薬を飲む統合失調症の患者さんにとってかなり不快なものです。しかし、副作用は薬ごとに多少の違いがあり、また個人差もかなり大きく、あらかじめ予想するのはなかなかむずかしいのが現実です。
これらの副作用はとくに服薬し始めたころに発現しやすく、しばらく服用していくと慣れが生じて、症状は軽減していきます。
もう一つやっかいな副作用として、錐体外路症状やパーキンソン症状とよばれる身体のこわばりやふるえなどがあります。
これは第2章の図で示したように、抗精神病薬が脳内にあるいくつかのドーパミン系をすべて抑制してしまうためです。ドーパミン経路が遮断されると、抗精神病作用が生じると同時に、黒質線条体ドーパミン経路の遮断により、錐体外路症状もひきおこされてしまいます。
とくに従来から使われている抗精神病薬は、投与量が多くなると、多かれ少なかれこの錐体外路症状をひきおこします。
また、プロラクチンというホルモンの分泌にもドーパミンは関係しており、抗精神病薬はそこに働いてプロラクチンの分泌を増加させます。そのために、女性では生理が止まってしまったり、乳汁の分泌などが見られたりすることもあります。
何年あるいは何十年と抗精神病薬を服用している患者さんの中には、口をもごもごしている人を見かけることがあります。
この、もごもごした口の動きはジスキネジアとよばれる不随意運動です。本人はあまり自覚していませんが、見た目はあまりいいものではありません。
抗精神病薬の長期投与によって発症することがあり、これを遅発性ジスキネジアとよびます。定型抗精神病薬はこの遅発性ジスキネジアをおこしやすいといわれています。
これも抗精神病薬による錐体外路症状の一つです。
スウェーデンのファルデという研究者は、第2章で紹介したPETという装置を使って、抗精神病薬を服用している患者さんの脳内のドーパミンD2受容体がどれくらい抗精神病薬によって占拠されているかを調べました(図4)。
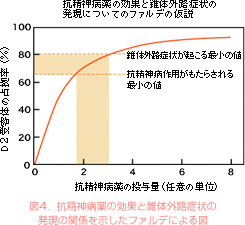
【図4】ファルデらは患者さんの線条体でドーパミンD2受容体がどれくらい抗精神病薬によって占拠されているかをPETで調べました。
そこの結果、この部位のD2
受容体が抗精神病薬によって75-80%以上占拠されると錐体外路症状が発生する一方、65-70%以上占拠されていないと、抗精神病効果が表れないことがわかりました。
従来の抗精神病薬ではこの曲線の立ち上がりが急なので、■部のちょうどよい投与領域(錐体外路症状はでないが抗精神病作用はある)を、個々の患者さんで予想することはきわめて困難です。
そうすると、大脳の線条体という領域(錐体外路の主要な部位です)で75~80%以上のドーパミンD2受容体が占拠されると、錐体外路症状が出現することを示しました。
抗精神病薬の投与量を調節して、この占拠率以下になるようにし、同時に少なすぎて抗精神病効果が消えないように、ちょうどよい投与量を見つけられればよいのかもしれません。
しかしそれを実際の治療場面で、個々の患者さんに対して行うことはむずかしかったのです。
このように従来使われてきていた抗精神病薬には、錐体外路症状とプロラクチン分泌という副作用が、程度の差はあっても必ず伴っていました。
これらの抗精神病薬を従来型抗精神病薬とか定型抗精神病薬などとよんでいます。
3-2-2新しい抗精神病薬-非定型抗精神病薬
従来からの抗精神病薬-定型抗精神病薬
錐体外路症状とプロラクチンの増加は、その薬物の抗精神病効果とは直接関係しません。
最近になって、このような副作用の少ない抗精神病薬が日本でも発売されるようになりました。
これらの薬物を従来からの定型抗精神病薬と区別して、非定型抗精神病薬とよんでいます。
アメリカでは抗精神病薬の多くの処方がこの非定型抗精神病薬になっているとのことです。
それではどうして非定型抗精神病薬は錐体外路症状などをひきおこしにくいのでしょうか。
現在はっきりと説明できませんが、一つの可能性として、非定型抗精神病薬は従来の抗精神病薬ほどドーパミンD2受容体に固く結合せず、ゆるやかに結合するので、もともと存在しているドーパミンの働きを阻止しすぎないからだろうという説があります(図5)。
あるいは、セロトニンとよばれる神経伝達物質にも作用して、セロトニンとドーパミンの相互作用から錐体外路症状がひきおこされにくくなっているという考えもあります。
また、一部の非定型抗精神病薬はドーパミン以外のいろいろな神経伝達物質の受容体に作用するので、その総合的作用の中から非定型な抗精神病作用がもたらされるのだという人もいます。
非定型抗精神病薬は、従来の抗精神病薬が苦手としていた統合失調症の陰性症状にも効果があるともいわれています。
しかし、これは錐体外路症状がないための見かけの改善なのか、それとも本質的な作用なのかについては、研究者のあいだで意見が一致しません。
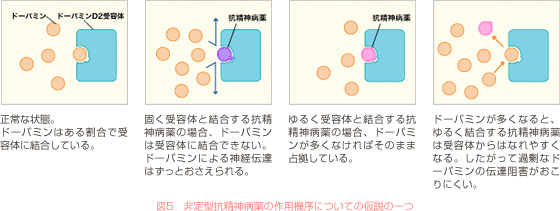
定型抗精神病薬はドーパミンD2受容体に固く結合するので、もともとあるドーパミンの濃度が変動しても関係なく受容体を遮断し続けます。
非定型抗精神病薬はこの受容体に緩く結合するので、ドーパミンが増加した際などには受容体から離れていきます。
その結果、過剰な遮断をひきおこさないので、錐体外路症状もひきおこしにくいのであろうと考えられています。
3-3これからの抗精神病薬
非定型抗精神病薬は錐体外路症状をひきおこさず、患者さんの側にとっても服薬しやすい薬なのですが、まだ理想の抗精神病薬とはいえません。
最近、非定型抗精神病薬の一部に血糖値を上げる作用のあることがわかり、糖尿病の患者さんには使いにくくなりました。
また、統合失調症の陰性症状や認知障害にたいしては、まだ効果が充分とはいえません。
ここでは、欧米ですでに発売されていて、日本でも発売になった新しい作用機序の抗精神病薬を紹介しましょう。
ひとつはドーパミン部分アゴニストです。
この薬物は錐体外路症状やプロラクチン分泌をひきおこさないので、非定型抗精神病薬に属するといってよいでしょう。
しかし、この薬物はドーパミンD2受容体を完全に遮断する作用を持たず、むしろ一部遮断しながら、一部刺激するという作用を持っているらしいのです(むずかしい言葉で部分アゴニスト作用といいます)。
そうすると、ドーパミンが多すぎるときにはその作用をおさえ、少なすぎるときには強めるということになります(図6)。
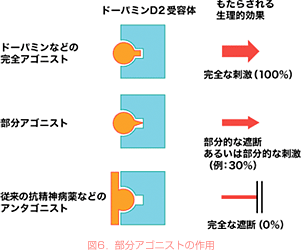
【図6】従来の抗精神病薬はアンタゴニストとよばれ、ドーパミンD2受容体に結合して、ドーパミンの神経伝達を完全に遮断します。
一方、もともとこの神経系にあるドーパミンはこの受容体を完全に刺激します。
部分アゴニストはこれらと同じように受容体に結合するのですが、アンタゴニストのように100%遮断するわけでもなく、アゴニストのように100%刺激するわけでもありません。
たとえば、30%の刺激(あるいは70%の遮断)のように、その中間の作用をします。
したがって、ドーパミンが少ない状態では部分アゴニストはドーパミン受容体を刺激するように働き、逆に多すぎる状態では抑制的に働きます。
そうすると、部分アゴニストはドーパミンの機能をちょうどよい状態に保つのであるといういい方もできるでしょう。
ドーパミンの機能をちょうどよいところに保つといってもよいかもしれません。新しい作用機序の抗精神病薬として注目されるところです。
これ以外にも、開発段階でいろいろな抗精神病薬の候補物質があがってきています。今までの抗精神病薬は多かれ少なかれドーパミンとの関連から開発されています。
将来、ドーパミン以外へ作用する新しい抗精神病薬は生まれてくるのでしょうか?ともあれ、今後はより副作用の少なく、従来の抗精神病薬が苦手としていた陰性症状や認知障害にも効果のある抗精神病薬の開発が望まれます。

